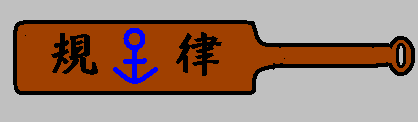
猪熊のラグビーの授業は本格的である。1年生のクラスでは、ボールに慣れることから始まり、最終的には(15人ではなく)10人対10人のミニゲームをできるようになるまで指導された。
各回とも基礎的トレーニングもかなり含まれるため、自然と基礎体力もついてくるのだ。そして、2年生では、フルスクラムやラインアウトといったよりパワーが必要であったり、より高度で複雑なテクニックが必要となるプレーとそのための基礎トレーニングを行っていく。
この基礎から懇切丁寧に指導する猪熊のやり方により、S大生はラグビー好きが多かった。すでに、体育実技のない3・4年生も、空き時間にはラグビーボールを持って楽しんでいる姿が、大学構内いたるところでみられた。
5月。大志たちの体育実技のクラスでもラグビーの授業が始まるところだった。
昼休み、自分たちの寮の部屋にもどり、ラグビーのユニフォームに着替える1年生たち。
大志が、203号室で、ユニフォームに着替えるため、ちょうどケツ割れサポーターを穿こうとしたとき、202号室の川原と、204号室の北村が入ってきて、
川原が、
「藤沢、おまえ本当にそのサポーター穿くつもりなのか?俺、それつけると、勃起しちゃうんだよ!」
北村が、
「ばーか!お前おかしいんじゃねぇ〜!欲求不満なんだよ!」
といって、川原の頭を小突いた。
「俺たちそのサポーターつけないから、お前もやめろよ!」
といった。
「規則違反だろ!もし、検査があったらヤバイだろ!」
という大志に、川原は、
「お前まじめだな!あんなの脅しだよ。それに、見つかっても、あの板で2〜3発ケツ殴られるだけだからたいしたことねぇ〜よ。山本先輩から竹刀で殴られる方がよっぽど痛てぇ〜ぜ。」
と言うのだった。
そこにいた2年生の宮元先輩も
「初回から、サポーターのチェックはしねぇから平気だぜ!俺たちの時は3回目か4回目だったな・・・。」
と言う。
大志も、「それなら、まあ、いいか・・・。」と、ケツ割れをつけずに、いつもの猫のイラスト入りのお気に入りトランクスの上にラグパンを穿いて、グランドに向かったのだった。
すでに、グランドには猪熊講師も出ていて、数人の1年生たちと話をしていた。
1年生のひとりが、
「先生、このパンツすこしピチピチすぎませんか、なんか窮屈で。すごく短いし。」
というと、猪熊は、
「ばかもの!お前たちのケツが締まっとらんのだ。おれの授業に1年間まじめに出席し、トレーニングをつめば、ケツも自然と引き締まり、そんなパンツ、スッとはいるようになる! スッと!」
と、その学生のことを一喝する。
猪熊は、しばらくして1年生が全員集まったのをみると、ホイッスルを吹き、集合をかける。そして、いきなり、
「よし、整列。 今日はこれから、お前たちが、そのラグパンの下に、ケツ割れサポーターを穿いているかチェックをする。パンツを脱ぐ必要はない。サポーターのケツの部分にかかるゴムを親指でパンツの外に出して、俺に見せるように!」
サポーターを穿いている1年生は、ケツ割れサポータのケツゴムを親指で掛けて、外に出して、猪熊にみせる。大志、川原、そして、北村以外は・・・。猪熊は、列の端から、学生たちのケツゴムを「よし!」「よし!」と次々にチェックしていく。だんだん自分の順番が近づいてくる。大志は、「や、やばい・・・」と思いながら、心臓がドキドキと鼓動を打つのを感じる。それと同時に、己の股間が、ドクンドクンと熱を帯びてくるのを感じるのだった。
果たして、猪熊は、大志、川原、北村たち3人だけがラグパンからケツ割れのケツゴムを引っ張り出して見せられないことに、気がつき、
「お前ら、サポーターはつけとらんのか!オリエンテーションで、ラグパンの下は、必ずケツ割れを穿くように言っただろうが!部屋に戻って穿いて来い!ほら、ダッシュだ!」
といって怒鳴るのだった。
ダッシュで寮の自室に戻り、パンツを脱いでケツ割れサポーターをつけ、グランドに戻ってくる。そんな大志たち3人を待ちかまえていたのは、右手に「規律」の文字が書かれた板を持った猪熊講師だった。
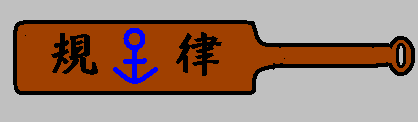
「お前たち三人は、そこに正座しろ。」といって、猪熊は、大志たちに、ケツ割れサポーターをつけることの重要性についての説教を始める。
そして、説教が終ると、
「説教だけで済むと思ったら、大間違いだからな!今日は、お前たちに、この規律と書かれた板で、規律を守ることの大切さを教えてやる!まず、お前ら三人は、用具置き場に置いてある木製の枠が付いた台をここに持って来い!」
と、大志たちに命令するのだった。
大志たちが、用具置き場にあったその台のような物を運んでくると、猪熊が説明を始める。
「これは、おれが製作した特製のスクラムマシンだ。2年生のクラスで、スクラムを組むときの練習用として使っている。」
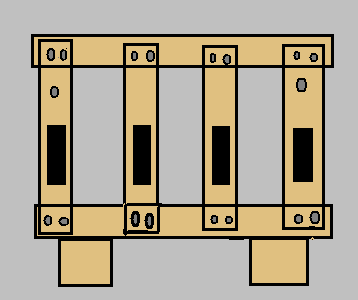
「本来は、フロント・ローは3人なんだが、今日は、お前たちに、ひとりずつ、このクッションに肩をあて、真ん中のところから顔を出し、ケツは後ろにしっかり突き出して、ケツ割れサポーターを穿いていなかった罰として、この板を、ケツに50発ずつ受けてもらうからな!」
「おい、おまえら、誰てもいいから、5〜6人でてきて、後ろの台に乗って、この台を固定しろ!」
1年生の列から、有志の学生5〜6人が、ニヤニヤしながら出てきて、マシン後方の台の上に乗り、スクラムマシンを固定するのだった。
「よし、まずは、藤沢、お前からだ!さっき言ったように、屈んで、そこのクッションに肩をあて、首と頭は前にだして、ケツを後ろに出せ!川原と北村は、そこで正座をして待つように!」
大志は、「はい!」と返事をし、立ち上がって、猪熊から言われたように、屈んで、スクラムマシンの縦板のクッションに両肩をつけ、両腕で縦板を抱えるように持ち、首と頭は前に出し、下半身は少し両足を開いて踏んばるようにして、ケツを後ろへ突き出し、ケツ叩き懲罰の位置につくのだった。ピチピチのラグパンの中で、大志の股間はまるで焼け石でもいれたように、硬く、そして、熱くなっていた。
「やっぱ、きちんとサポーター穿いとくべきだったよな・・・なにが、2,3発だよ・・・50発じゃんか・・・竹刀よりも、痛いのかなぁ・・・あぁ・・・」
などと、後悔しきりだった。
「一発目いくからな!歯をくしばれ!」
大志が、顔を上げると、前にはスクラムマシンを支えている同級生たちの顔と表情がみえる。無表情なヤツ、声には出さないが「ガ、ン、バ、レ」と口を動かしながら大志に同情的な視線をむける八つ、薄笑いを浮かべ「ざまぁみろ」とでも言いたげな顔をしているヤツもいる。
猪熊講師は、大志がケツをしっかりと突き出し構えたのを見ると、
「他のものは、数を数えてやれ!」と命令し、右手で「規律」とかかれた尻打ち板を振り上げ思い切り大志の右ケツに振り下ろすのだった。
バチン!
という音とともに、尻打ち板が大志のラグパンの右ケツを強襲する。熱い衝撃が、大志のケツから頭のてっぺんへと伝わる。思わず、「痛てぇ〜!!」と身をすくめ、スクラムマシンの木の枠を握り締める大志。無意識のうちに、大志は、そのスクラムマシンを両肩で前に押していた。
学生たちの「1!」と数える声が、グランド中に響き渡る。
何も言わない大志に、猪熊講師は、
「ほら、仲間に回数を数えてもらっているんだろ!クラスの奴らに礼をいわんか、礼を!」
大志は、やっとの思いで、
「あ、ありがとうございました!」
と、大声を絞り出す。礼を言うのが、終ったか終らないかのうち、二発目が、今度は大志の左ケツを強襲。
バシッ!
そして、
「2!」
と、クラスの声がグランドに響き渡る。
「ありがとうございました!」と、大志のあいさつ。
そして、大志のラグパンでピッチリ覆われたケツの双丘のちょうど真ん中に、3発目が振り下ろされる。
バチィ〜ン!
「3!」
「ありがとうございました!」・・・・・・・
グランドから響き渡ってくる数を数える1年生たちの声に、大学構内の上級生たちは、
「あ、今年もまた熊さんのクラスで、尻打ちの懲罰がはじまったなぁ!」
とニヤニヤ笑っている。
空き時間の上級生たちは、1年生たちのクラスで行われている、毎年恒例の尻叩きの行事を見物するため、続々と、グランドに集まってくるのだった。
その中にいた、大志と同部屋の3年生・田中太朗は、
「あれ!あいつ、俺らの部屋の藤沢じゃん!かわいそうに!」
同じく、見物にきていた、宮元進は、
「藤沢に変なこといっちまったかな!まぁ、いっか!」
大志の尻叩きは進み、グランドに響く、尻叩き板のケツ打音と、学生たちのカウント、そして、回数を増すごとに悲鳴のようになってくる大志の雄叫び。
バシッ!「22!」「ありがとうござました。」・・・・
バシッ!「35!」「ありがとうござました。」・・・・
バシッ!「47!」「ありがとうござました。」・・・・
ライト、レフト、センター と、大志のケツに、猪熊の「規律」板が、情け容赦なく振り下ろされていった。
真っ赤な顔をし、額から汗を流して、恥ずかしさとケツに絶え間なく襲ってくる痛みに耐える大志。30回をすぎる頃になると、板がドッシとケツに当たる感じはあるものの、ケツペタが麻痺してきたのか、痛みはそれほど感じなくなった。
そして、最後の一発が、大志の左ケツに炸裂する。
バシッ!
「五十!」
「ありがとうございました!」
その場に倒れこみそうになる大志。グランドの外で見物している上級生たちからは拍手が聞こえてきた。
やっとのおもいで立ち上がり、ケツの痛みを我慢して、再び正座する大志。
猪熊講師は、「よし!次!川原、位置につけ!」と命令する。大志へのケツ叩きを目の当たりにして、震えながら、半泣き状態の川原は、スクラムマシンに肩をつけ、ケツを後ろへ突き出し、仕置きに備えるのだった。
このようにして、猪熊の言いつけを守らなかった3人のケツにはキツイお灸がすえられた。
さらに、猪熊は、3人を叩き終わると、大志たちに、ラグパンとジャージを脱ぎ、ケツ割れ一丁で、大学の敷地の外周を取り巻く遊歩道を、三周、罰ランニングしてくるよう命じた。
真っ赤な顔をして、グランドをでて、ランニングを始める大志たち3人。黙って罰ランを始める大志たちに、猪熊は「オラァ!S大の掛け声はどうした!ワッセ!ワッセ!だろ!」 と怒鳴るのだった。
哀れ大志たち3人は、ケツ割れのケツゴムに縁取られた真っ赤なケツを後ろに晒しながら、「ワッセ!ワッセ!」と、ケツ叩きのあとの、恥ずかしい罰走の試練に耐えたのであった。
上級生たちからは、
「ガンバレ!根性だ!」
「男だろ!もっと元気に声出せ!ワッセ!ワッセ!」
「おまえら、ケツが真っ赤だぞ!どした?ワハハハ!」
と、応援やからかいの声が次々と飛んでくるのだった。
その晩、部屋の先輩からも、真っ赤なケツでの罰走のことを、散々からかわれた大志であった。そんな中、椅子に座るのもつらそうな大志に、山田先輩は、
「大志、ケツ見せてみ!」
といって、ズボンとトランクスをおろした大志のケツを「診察」する。
「ああ、アザになっちゃってる。いい塗り薬があるから、塗ってやるよ!宮元、医務室に行って、SP軟膏もらってきて!」
と、2年生の宮元に言うのだった。
塗り薬と聞いて、大志はインキンのときのことを思い出し、
「え、またしみるヤツですか?」
と、山田先輩に聞いた。
「心配するな!俺たちが1年生のとき、竹刀で殴られた後、よくぬっていた軟膏だ。少しは楽になるぞ!」
と山田先輩。
しばらくして、医務室からSP軟膏を持って戻ってくる宮元。それは、ケツを叩かれて熱ったケツペタの皮膚に塗ると、ケツペタの皮膚にじんわりと浸透して、発熱と炎症が鎮めるゲル状軟膏だった。山田先輩は、SP軟膏のチューブを握り、右手のひらの上に、たっぷりとゲル状のSP軟膏を搾りだすのだった。そして、大志のケツにやさしく塗ってやる。
「あっあぁ・・・いっ、痛い・・・も、もっと・・・や、やさしく・・・」
「こいつ・・・甘えやがって・・・」
山田先輩のSP軟膏がたっぷりついた右手のひらが、大志の左右・両ケツペタの双丘を、やさしく滑るように撫でていく。最初はちょっと擦れて痛かったが、だんだん慣れてくると、ケツがスゥ〜として気持ちよかった。大志は、いつも兄貴のように思っている山田先輩から優しくしてもらって、不思議と、股間が熱くなり、イチモツが硬くなってきれしまう。それが、山田先輩に バレないか、気が気ではなかった。
山田先輩は、SP軟膏を大志のケツに満遍なく塗り塗りするように、大志のケツをやさしいタッチで撫でまわしながら、
「あぁ、こんなにケツが腫れちゃって・・・今夜はうつ伏せで寝た方がいいぞ・・・熊さん、容赦なしだからな・・・でも、あれでも、だいぶ丸くなったんだぜ。」
と言い、3年前の猪熊講師の体育講義の話をはじめるのだった。
猪熊講師は体育講義も受け持つ。しかし、前章で述べた理由から授業内容は大幅に端折られており、講師自身の著書「猪熊三郎の運動生理学入門」を買わされ、
「このテキストの第3章から第9章までが学年末試験の範囲だからだ!試験までには、各自でよく読んで自習しておくように!」
といわれるだけだった。
ただ、そうはいっても、将来、船乗りになるという観点から、時折、教室または体育館での講義も行われたのだ。その柱は2本で、一つは、心肺蘇生法などの救命応急処置の実習も兼ねた講義。そして、もうひとつは、性病とその予防法に関する講義であった。
3年前、新任講師として、猪熊の母校・関東体育科学大学から、S大学へ転任してきた猪熊。その粗野で過激な言動から、 母校の関東体育科学大学では研究室の主任教授から疎まれ、若手ホープとして助教授に抜擢されてもいい研究業績をもっていたにもかかわらず助手の地位に甘んじていた。S大学の講師への転任も、「椅子」の上では昇格であるが、実質は、左遷であるとS大学の教授会や教務掛のあいだではもっぱらの噂だった。
母校で主任教授から「猪熊君、君ももっと大人になってもらわねば困るよ。」と叱責をうけても、ラグビー部の合宿所でのノリで、「ウッス!」と答えてしまう始末の猪熊であった。体育大学とはいえ、大学のアカデミックな雰囲気になじむはずもなかった。
当時1年生だった山田勝昭のクラスでの保健体育講義では、
「よし、鬼頭!前に出て来い!本日の体育実技に、ケツ割れサポーターを穿かずに出席した罰として、これから実演講義のアシスタントになってもらう!」
と命令し、教室の前に出てきた鬼頭に、
「これから、お前の大事なイチモツをつかい、正しいコンドーム装着法を示説する!」
という猪熊。教室の学生たちから、大爆笑が沸き起こる。
大笑いの学生たちを鎮めるかのように、猪熊は、
「示説のあと、お前らにも自らのサオを使って、ここで、コンドーム装着実習をしてもらうかな!よくみておくように!イチモツに正しく装着できないヤツは不合格だ!体育講義の単位はやらんからぞ!」
と警告するのだった。
「よし、鬼頭!そこで、スッポンポンになれ!」
真っ赤な顔をして、モジモジしている鬼頭に、
「オラァ!グズグズすんな!人前で全裸になるくらい、もう寮でなれてるだろう!」
と、猪熊の喝が飛ぶ。
そして、なんと、裸になった鬼頭に、
「よし、竿、起てぃ!」
と命令するのだった!!再び、学生たちからは、大爆笑!
緊張と羞恥心から、完全に萎えてしまっている鬼頭のモノをみて、猪熊は、
「おまえ、サオの起て方もしらんのか!男としての修行がたりん!おれが、おっ勃起ててやる。」
といい、鬼頭の後ろにまわり、鬼頭に目をつむるようにいうと、猪熊は、
「ほら、前にすわっている奴らのことなど気にするな!好きな女の裸を想像するんだ!今は野郎だらけのつれぇ寮生活だが、娑婆に置いてきた彼女の一人くらいお前にだっているだろう・・・」
と言うと、後ろから手を伸ばし、鬼頭の萎えたサオを右手でわし掴みし、しごき始めるのだった。さらに、左手では、鬼頭の玉を掌の中でころがすように揉み始める。これには、さすがの鬼頭も、たまらんとばかり、鬼頭のイチモツは、たちまちシュィンと、勃起屹立したのであった。
「おっと!やっと元気になってきたな・・・おお、そのくらいだ・・・そこで止め、止め・・・これ以上は気分だすなよ・・・」
と、鬼頭に言うのだった。鬼頭は、同期の学生たちの前で、教官の手コキで勃起させられた恥ずかしさからなのであろう、真っ赤な顔のまま、ジッと両目をつむったままだった。
猪熊は、さらに、
「鬼頭は、Lサイズのコンちゃんだな!なかなか、立派なものを持っていて、将来が楽しみだ!」
などと言い放つ。学生たちは大爆笑。
「おっ!鬼頭!この巨根野郎!!」
と、野次も飛んでくる。
猪熊は、ニヤニヤしながら、コンドームをとると、鬼頭の屹立した竿を使い、正しいコンドーム装着法の実演を始める。
正しいコンドーム装着法の説明をしながら、コンドームの先端をしっかりと押さえ、毛深くごつい手ににあわない、指先の滑らかで繊細な動きで、コンドームの末端をスルスルと鬼頭の竿の根元まで下ろし、鬼頭の竿にコンドームを正しくピチっとかぶせてやる猪熊講師だった。
己の竿の先端から根元まで、なめらかにすべらせるようにコンドームをかぶせていく、猪熊の指先の撫でるようなソフトなタッチに、鬼頭は、思わず、
「あっ、あぁ〜!」
とあえぎ声をあげてしまう。
「コラッ!なにを気分だしとるんだ!ばかもん!このくらい辛抱せい!」
と、鬼頭のケツを平手でバシッ!とたたく猪熊。再び学生たちからは大爆笑が沸き起こるのだった。
鬼頭のイチモツへのコンドーム装着が終わると、猪熊は、学生たちに指示を出す。
「よし、鬼頭は戻ってよい。これから、おまえたち一人一人にもやってもらうからな!前にコンドームがあるので、自分のサイズにあったものを、ひとつずつ選ぶように。サイズは、SS、S、M、L、LL 、そして、バズーカだ。残念ながら、イボイボの付いたやつはないからな!ほしかったら、駅前の薬局で自分で買うように!それから、見栄をはって、でかいのを選ぶなよ!あとで、ひとりひとり、おれがチェックしにいくからな!ピッタリと竿にフィットしていなければ、不合格だぞ!」
山田たち1年生は、教室のまえに置いてあったコンドームを一つ一つとる。1年生たちが取り終わると、猪熊は、
「全裸になり、サオを起てろ!」
と、学生たちに命令するのだった。
体育講義の単位がかかった実習だ!鬼頭を除く学生たちは、全員、下はフリチンとなり、真っ赤な顔をして、自らのモノを扱き、勃起させようとしている。なかなか、自分のモノを勃起てられない者には、猪熊講師は、鬼頭にやったの同じように、後ろに回り、猪熊自らの手で、手伝ってやった。なかなか、コンドームを装着し終わらない1年生たちに、猪熊は苛立って、
「お前ら、コンドーム一つ己の竿につけるのに、何時間かかっとるんだ!そんなことじゃ、女はとっくの昔に逃げちまってるぞ!!」
と、一喝するのだった。
ようやく、学生全員がコンドームを装着し終わると、猪熊が、一人一人の装着状況を検査していく。
「サイズが合っとらん!お前は、SでなくMサイズだろうが、もっと自分の持ちものに自信を持て!」
「先端に空気が入っていてダメだ!これじゃ、いざ鎌倉という時、破れて漏れちまうぞ!」
などと、ダメ出しを学生たちに入れていく。やり直しを命じられる1年生がほとんどだった。その度に、猪熊の右手が、1年生たちのケツにバチッ!と飛ぶのだった。
山田自身も、3回ほどやり直しをさせられ、やっと合格となった。
なかなかうまく装着できず最後まで残った5人は、コンドームを無駄使いした罰として、講義終了時に、竹刀でケツを5発ずつ殴られた。
しかし、このコンドーム装着実習は、S大学の教授会から、あまりにも過激だとのクレームがつき、翌年からは、竹刀の先端を使った、コンドームの装着法実演のみとなったそうである。
当時の実習の様子を懐かしそうに話す山田先輩に、宮元先輩は、
「え!鬼頭先輩って、1年生の時、そんなことやらされたんスか?」
と、ニヤニヤしながら言うのだった。
山田先輩は、
「ああ、それ以来、鬼頭のヤツ、熊さんには頭が上がんないらしいぜ!まあ、アイツの唯一の汚点だな!ワハハハ!」
と笑い飛ばす。
大志は、山田先輩のその話を聞いて、さっきから硬く熱くなっていた股間が、さらに、熱くなり、今にも爆発しそうになるのを必死で我慢しているのだった。